仕事のモチベーションが下がる理由
前企業には約25年(営業職10年、管理職15年)勤務しました。
その間多くの社員が仕事のモチベーションをなくし、退職しました。当時私が直接ヒアリングした退職理由をみながらこの問題を考えたいと思います。

ヒアリングした退職理由
| 23歳 男性 | 入社前の会社説明と実際の現場営業のギャップがあった。 |
| 25歳 女性 | 会社の理念やビジョンは共感できるが、目の前の仕事に忙殺されて何をしてるのか分からなくなった。 |
| 30歳 男性 | 会社として差別ができる商品が少ない。自分の営業力で差別するのも限界がある。 |
| 23歳 男性 | 入社して仕事内容が向いてないと感じた。取引先や顧客と接することが苦痛である。 |
| 30歳 男性 | 7年間仕事をしたが、この会社でずっと働くイメージが湧かなくなった。 |
| 35歳 男性 | 企業としての競争力が欠如していると感じた。精神論で営業をすることに疲れた。 |
| 33歳 男性 | 後輩に役職を抜かれ、仕事がやりづらいし、やりがいを持てなくなった。 |
| 40歳 男性 中途 | 今までのスキルや知識が生かせやりがいある仕事だと思ったが、実際は違った。 |
| 29歳 男性 | この仕事は好きだが、自分の将来像が見えないと感じ始めた。 |
| 38歳 男性 中途 | 実績を上げ続けているにも関わらず、評価が低い状態が続いたから。 |
| 26歳 男性 | 上場企業でホワイト企業と思っていたが、営業現場では数字の詰めばかりで辛くなった。 |
| 38歳 男性 | 同期が管理職になっていく中で、自分だけが営業職で残っている。今後のキャリアプランが見えない。 |
| 43歳 男性 中途 | 自分の部署はそもそも評価低い。やって当たり前という感じに思われている。自分のスキルと知識を生かせるところに転職したい。 |
| 33歳 男性 | 上司との相性が悪い。同じように仕事をしていても自分にだけ難癖を付けてくるので、我慢の限界だ。 |
退職理由からの考察
上記の退職理由をまとめてみますと、「企業の理念やビジョンと現場での業務内容の乖離」「職場環境」「正当な評価を受けてない」「企業でのキャリアプランが見えない」「仕事が向いてない」「企業の商品力が低い」となります。
企業の理念やビジョンと現場での業務内容の乖離
これは私も感じていたことです。
「企業がこの理念を元に、今後こんな風になっていく」ということに共感してました。
ただ日々の業務が、そのビジョンに繋がっている気がしないのです。
ゴールがあって、そこに向かうためのプロセスを踏めばゴールに到達するものですが、日々の業務をしても企業が目指すビジョンにたどり着く気がしないのです。
これは企業として致命的です。
上場していたので四半期毎の決算発表の数字づくりが必要ですが、この数字づくりが目的となってました。
企業は社会の課題を解決するために、理念やビジョンを掲げるものです。
理念を元にビジョンを達成すれば社会の課題が解決でき、それに伴い収益が上がる、というのが本来の姿です。
営業現場で商材やサービスを売ることによって、企業のビジョンは達成されるものです。
しかし企業が数字を求めるため、企業のビジョンが達成できるとは思えない、むしろ逆効果の商品やサービスを売ることを求められました。
上場企業は、株主やアナリストから評価されなければなりませんので、増収増益を目指さなければなりません。
しかしその為に売る商材やサービスが逆効果のものであれば、企業のビジョン達成や社会の課題解決が遠のくだけです。
往々にして中期経営計画の策定は経営陣、担当部署(経営企画部等、場合によってはコンサル会社)で策定します。
「右肩上がりの売上利益」「こんんな取り組みをします」など、株主やアナリストの耳障りのよい数字や取り組みが並びます。
現場からすれば、「根拠のない数字」「意味のない取組」と映っていることがほとんどです。
ではどうすればよいのか、
中期経営計画こそ、現場からの意見(ボトムアップ)で策定すべきものです。
ボトムアップで策定したものであれば現場はコミットします。
コミットしたものであれば現場は達成すべく動きます。
但し、このコミットした数字や取組が株主やアナリストの期待に沿ったものではないかもしれません。
また企業としてのビジョンを達成するためには、このコミットでなければならないことを説明するのが経営陣の役目ではないでしょうか。
社員が仕事にモチベーション持って取り組む職場環境は、経営陣が主導して作らなければなりません。
また役職者も現在の職場環境に疑問や問題があるのであれば声を上げるべきです。そうしなければ社員は去っていきます。
職場環境
本社から離れた拠点(支店や営業所)では、そこのトップがよくも悪くも、その職場環境を作ります。
またどこに配属されるかは神のみぞ知るで、上司を選ぶことはできません(勿論、逆もそうですが)。
相性が合わなければ最悪です。
もう我慢するしかないのです、耐えるしかないでのす。
私は5年で解放されましたが、いつメンタルになってもおかしくない状況でした。
解決方法は、何度も書いてますが、人事部やハラスメント窓口へ相談することです。
これで企業が動かなければ、その企業で働く意味はないです。
モチベーションを持って仕事をしたい人に対する冒涜ですので、さっとと転職しましょう。
正当な評価を受けてない
会社員としての運命を決めるのは、「自分を引き上げてくれる上司と出会えるか、出会えないか」「また引き上げてくれた上司が出世するか、しないか」です。
実績を上げても人事評価、昇格、昇進等々で、実績を上げていない人が評価されることもあります。
また、いつ自分を引き上げてくれる上司と出会うかですが、運とタイミングだと思います。
但し、大切なことはそのために地道に、ひたむきに仕事をすることです。
これは私の経験上ですが、実直に仕事をしている姿を見ている人は必ず居ますので、腐らず仕事を続けてはいかがでしょうか。
キャリアプランが見えない
私が入社して暫くの間は、企業も上場したばかりで、業績も右肩上がり、やればやるだけ評価をされるし、顧客にも喜ばれる、という職場環境で、すごく楽しい時期でした。
また人も規模も急拡大した時期だったので、人事制度構築が追いつかず、実績を出せば昇給、昇格、昇進をガンガンしていました。
ただ入社して15年程経過したころから業績も大きく伸びず、閉塞感が漂うようになりました。
その頃になると人事制度もしっかり構築され昇格、昇進の基準も明確になりましたので、以前は最短30歳で管理職もあり得たのですが、35歳が最短で40歳がスタンダードとなりました。
また新卒ですと同期の人数も多いため、出世争いも熾烈になっていきました。
そうなると管理職になれそうにないと思った人のモチベーションがなくなり、退職に繋がっていきました。
またその状況を会社が把握し、解決策を出すまでに時間が掛かりました。
様々なキャリアプラン(管理職にならず専門職の選択枝等々)が出てきたのは数年後でした。
この仕事に向いてない
この仕事に向いていないと退職した人は、毎年新卒の中に数名いました。
特に有名大学出身者に多かったです。
確かに、入社前の企業案内時に共感した企業像と現場での仕事内容が乖離していると、そうなるよな~といつも思ってました。
有名大学出身者で頭もよいので、公務員試験に受かりましたとか、上場企業に転職が決まりましたとか、で早々に退職していきました。
このままモチベーションがなくなるまで仕事をするよりも、早いうちに自分に合う企業と出会う方がよいと思いますので。これはこれでよいと思いました。
企業の商材力が低い
いろんな商材とサービスを扱ってました。その商材やサービス1つ1つの専門企業もありましたので、そこと競合となると商材力で負けました。
例えば、
X社には、A、B、C、Dという4つの商材があります。
A、B、Dは専門で取扱っている企業が多く、CはX社が先行して作ったビジネスモデルで優位性のある顧客ニーズの高い商材。
またY社はA商材を専門で取り扱ってます。
Y社が、Z顧客にA商材を売る時にはコストや性能をアピールします。
X社はコストや性能で負けるので、Xにとって必要かは分からないがB、C、D商材も同時にアピールします。
結果、B、C、Dに興味が無ければ撃沈します。
しかし、C商材いいね、ということになればセットで売れる、という感じです。
C商材が独占で顧客ニーズの高い商材であった時には、他商材も一緒に売れてましたが、競合他社が出てきた途端、優位性を失い売れなくなりました。
企業が優位性をいつまでも保つことができると勘違いしていたこと、そのことにより次の商材開発が遅れたこと、その結果、前述したビジョンを達成するための商材ではない物やサービスを現場では売ることになり、現場の仕事に対するモチベーションがなくなりました。
仕事のモチベーションを取り戻すために
なくなった仕事のモチベーションを取り戻すための方法を考えてみたいと思います。

企業体質の改善
会社員の仕事へのモチベーションを上げれるのは経営陣、そしてある程度の役職者です。
以下のような改善をして貰いたいものです・・・
売上、利益も大切ですが、一番大切なものは理念に基づいたビジョンの達成(=社会課題の解決)です。
トップダウンの中期経営計画では、現場は腹落ち感がありません。現場からの声を反映したボトムアップの中期経営計画であればモチベーションを持って動きます。
その商品、サービスを顧客へ売ることで企業のビジョンが達成できるのか、もしできないものであれば売らせてはいけません。
企業の継続、拡大には「人材育成」が不可欠です。その人材をハラスメントで「人材廃棄」にしては企業の存続が危ぶまれます。
様々な価値観を持つ社員が増えてます。それに伴い企業は様々な働き方の選択枝を準備し、社員が活躍できる場を提供する必要があります。
引き上げてくれる上司の存在は絶対です。引き上げるにしても納得感ある人事制度が整備されていることが前提です。年功序列もなくなり、かつての部下が上司になる時代になりましたので、そういう意味でも矛盾の生じない納得感ある人事制度の整備が大切です。
選択肢を考える
評価されない、この仕事に向いていない、職場環境が良くない等々、思うことは色々あると思います。仕事のモチベーションが一度下がると、上げることはなかなか難しいと思ってます。
モチベーションが上がらない中でも地道に仕事をした結果、昇格したり栄転した人は再度モチベーションを上げ、仕事を続けることができていました。
しかし今までの経験上、モチベーションがなくなり、一旦退職を考えた人は100%退職しています。
当然ですが、企業体質や職場環境が改善されないことは、自分ができることの範囲外であり、そこに労力や時間を掛けても意味がありません。
自分のできる範囲内で努力をすることが大切です。
よってそのまま地道に実直に仕事を続けるのか、退職して充電期間を作るのか、新天地を求め転職するのか、検討してみましょう!
にほんブログ村

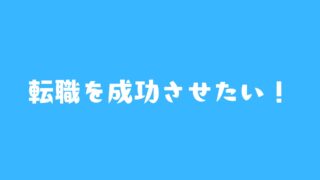
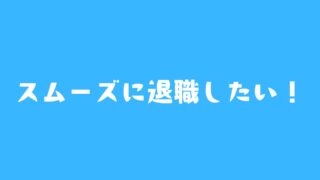

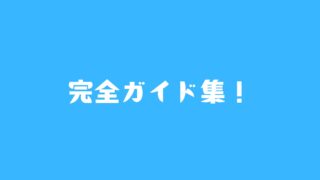
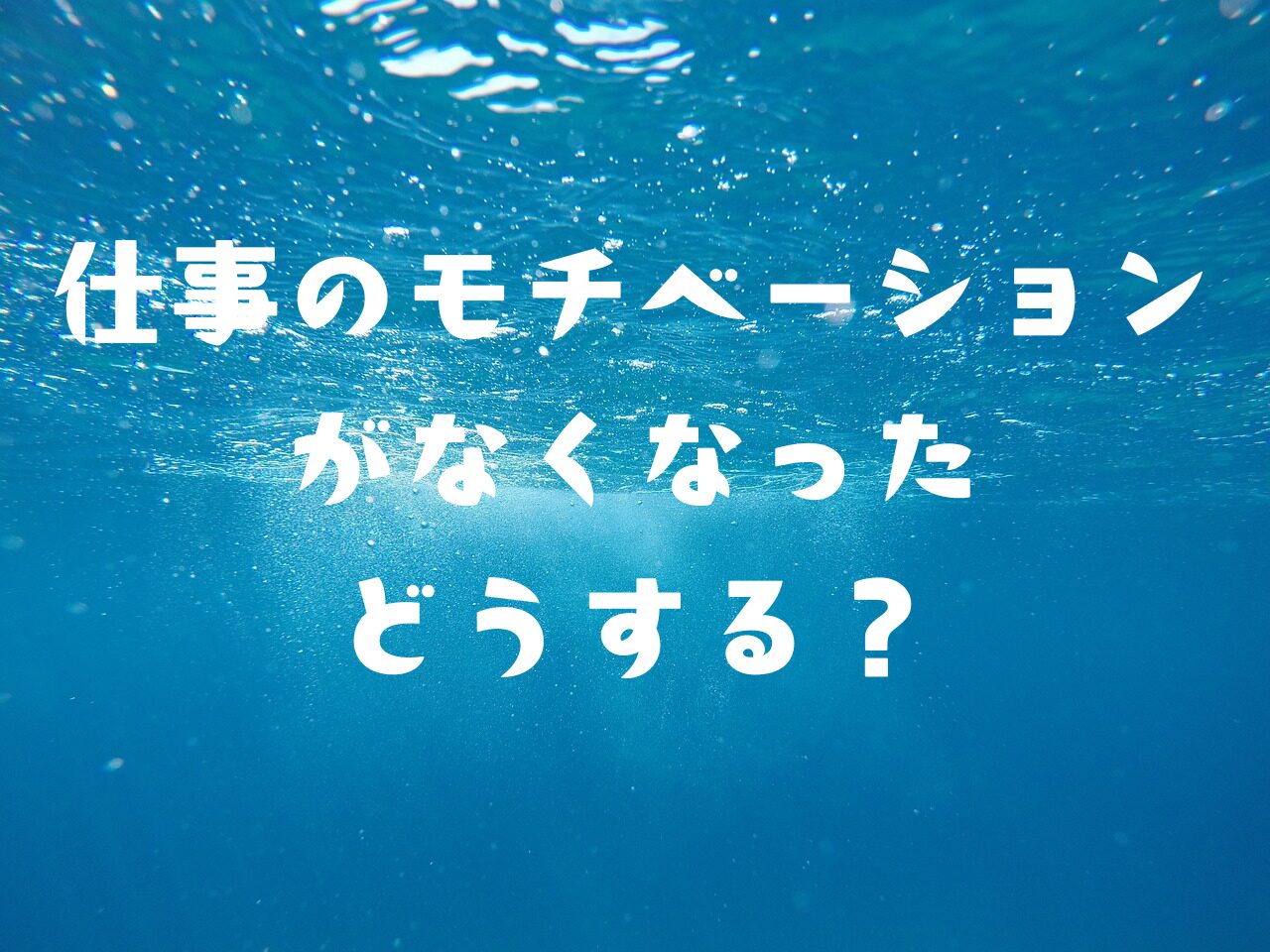


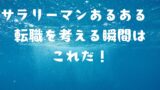


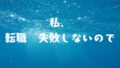

コメント