転職活動って、まるで恋愛みたいなものですよね。
面接は初デート、内定はプロポーズ、入社は結婚…そして、転職失敗は——離婚です(泣)
「この会社、運命かも!」と思って転職したのに、実際は理想と現実のギャップに打ちのめされたり、またすこしブラックテイスト入っていたり・・・ということってあるかもしれません。
今回は、私が様々な転職経験者から聞いたそんな転職の「失敗あるある」を、笑いと涙を込めて一気にご紹介します!
- アットホームな職場って書いてあったから期待したのに、ただの監視社会
- 「年収アップ!」って言ってたけど、残業代込みだった件
- 「風通しのいい会社」=声のデカい人がすべてを支配
- 「土日休み」って言ってたのに、実態は365日ほぼ繁忙期
- 面接官の笑顔にダマされる
- 「研修制度あり」と書いてあったが、実態は「放置プレイ」
- フラットな組織です!=役職名がないだけで社長が神
- 前の会社のほうがマシだったかも…と気づくのが早すぎる
- 試用期間中に「やっぱ合わない」と悟るが、次の転職活動する気力ゼロ
- 内定もらった時のワクワクが、初出勤5分で消える
- 「自由な社風」に期待 → ただの放任主義だった
- 社内イベントが多すぎて、プライベートがない
- うちは離職率低いですよ!
- 入社初日に「え、これ一人でやるんですか!?」案件を任される
- 「一生ここで頑張る!」と宣言したのに、半年で転職サイトを再び開く
- 失敗も経験値になる。転職は“旅”だ!
アットホームな職場って書いてあったから期待したのに、ただの監視社会

求人票の常連ワード「アットホームな職場」
これ、転職活動中の心にグサッと刺さる甘い響きですよね。
「今度こそ、温かい仲間と一緒に働けるんだ!」なんて、入社前はワクワク。
……でも現実は、まさかの“家庭的”じゃなくて“親戚の寄り合い型監視社会”だった、というパターンが多いんです。
アットホーム=仲良し、ではなく。
アットホーム=全員の行動が筒抜け&プライバシーゼロのことだったりします。
たとえば・・・
- 昼休みに一人で外食したら「なんでみんなと食べないの?」と詰問される
- 定時で帰ると「え、もう帰るの?うちらまだ残ってるけど?」という空気が発生
- 休憩中にスマホをいじっていたら、全員がのぞき見をしてくる
・昼休みに一人で外食したら「なんでみんなと食べないの?」と詰問される
……はい、完全に監視社会です。
まるで小さな村の中で暮らしているような閉鎖感。
「家族みたいな職場」って、実際は「干渉の激しい親戚のおばちゃん集団」みたいなもんだったりするんですよね。

本当にアットホームな職場って、わざわざ求人票に書かなくても伝わるんですよね。「うち、アットホームなんですよ〜」と強調してくる会社ほど、ちょっと身構えたほうが安全かもしれません。
「年収アップ!」って言ってたけど、残業代込みだった件

転職先を選ぶときに、多くの人が注目するのが「年収」。
求人票にでかでかと書かれた「前職より年収アップ!」の文字。
その瞬間、頭の中には豪華なディナーや旅行、ちょっといい家電の妄想が広がります。
しかし、実際に入社して明細を見てみると・・・
「え、これ……残業代込みってこと!?」と目を疑うこと、ありますよね。
よくあるパターンとして
- 基本給がやたら低いのに、「想定年収」には毎月45時間分の残業代が含まれている
- そもそもその45時間を残業しないと“想定年収”にならない仕組み
- 実際は残業がもっと多くて、時給換算したら前職より安いというオチ
つまり、「年収アップ」は幻想で、実態は「労働時間アップ」だったりします(苦笑)
求人票には「みなし残業込み」「固定残業◯時間分を含む」などの記載があるケースが多いですが、さらっと書かれているので見落としがちです。
しかも厄介なのは、「残業込みの年収」であることを面接時にハッキリ言わない会社もあります。
面接で「頑張ればもっと稼げますよ!」なんて言われると、ついテンションが上がってしまいますが、実は頑張らないと稼げないという仕組みになってる場合があります。

転職では「年収額」だけでなく、内訳と労働時間を見る目が超重要です。数字だけで飛びついたら、ブラック企業のワナだった──これ、あるあるです!
「風通しのいい会社」=声のデカい人がすべてを支配

もう一つの転職ワードの定番、「風通しのいい会社」。
これを見て、「意見を言いやすい、フラットな会社なんだな」と期待する人、多いですよね。
ところが、実際は “声のデカい人の意見だけがスルスル通っていく会社” だった、というパターンも珍しくありません。
「風通しがいい」は本来、組織の情報や意見がスムーズに流れて、上下関係もオープンで話しやすい状態を指します。
しかし、現実はこう
- 会議で意見を言ったら「そういうのは今はいいから」と即スルーされる
- 上司の古参社員の意見が絶対正義
- 「自由に意見していいよ!」→ 実際に言うと、そのあと妙に距離を取られる
つまり、「風通しがいい」というよりは、「一方通行の風が吹いている」状態。
強風(=権力者の意見)には誰も逆らえないんです。
特に中小企業やスタートアップでは、「社長や役員の意見=会社の方針」という構図が強く、
結局、みんながイエスマンになっていく…というケースもよくあります。
本当に風通しのいい会社は、声の大きさじゃなくて意見の多様性と対話の文化で成り立っているんですよね・・・

求人票に「風通しがいい」と書かれていたら、「どんな意見が実際に通るのか」「誰が決定権を持っているのか」を面接で具体的に聞くことをお薦めします。
「土日休み」って言ってたのに、実態は365日ほぼ繁忙期
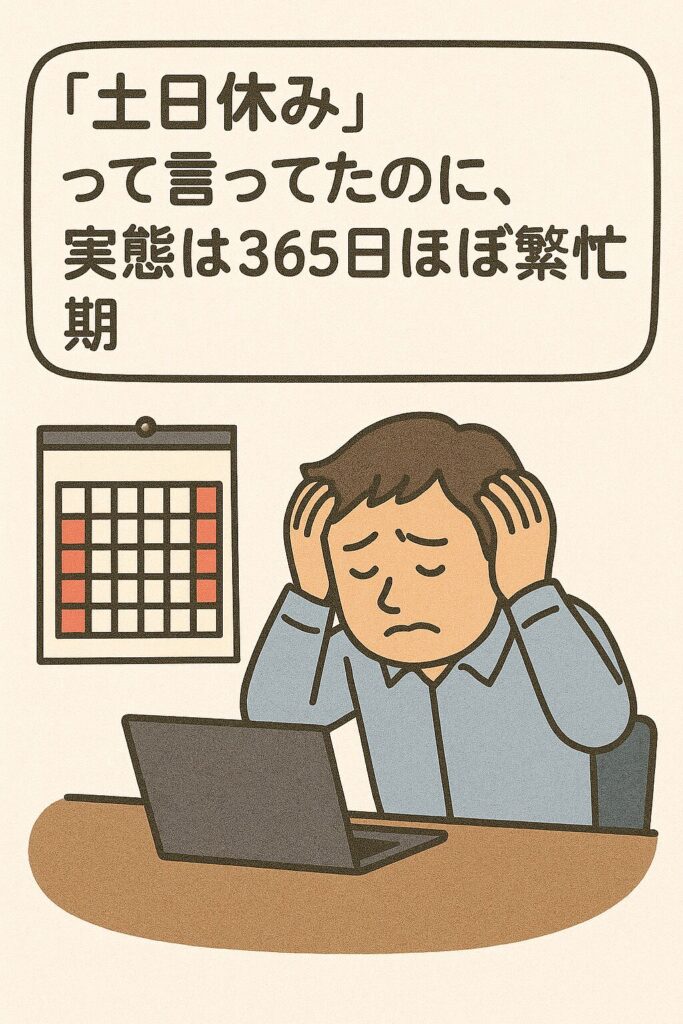
求人票で「完全週休二日制(土日休み)」と書かれていると、「週末はゆっくりリフレッシュできる♪」と期待しちゃいますよね。
でもいざ入社してみると──
「土曜は“勉強会”があるから来てね!」
「日曜は“自主参加”イベントだから、できれば全員来てほしい」
「繁忙期だから…」が常套句で、繁忙期が終わる気配がない
……え? これ、いつ休むの??
特に中小企業や営業職にありがちなのが、暗黙の休日出勤文化。
「出勤」とは言わないまでも、イベントや打ち合わせが頻繁に入っており、実質的には週休ゼロに近い働き方になるケースです。
さらに恐ろしいのが、「自主参加=強制参加」パターン。
断ると「やる気がない人」と見なされる空気があり、誰も断れない…。
休日のはずなのに、なぜか上司や同僚と会ってるという、なんとも言えないモヤモヤ感が残ります。

面接時に「休日出勤はありますか?」と聞いても、「繁忙期だけだよ!」と笑顔で答えられると安心してしまいがちですが──その繁忙期が1年中続くこともあるので、ちゃんと期間を確認しましょう!
面接官の笑顔にダマされる

転職活動の面接って、いわば「恋の初デート」みたいなもの。
お互いにいい顔をして、ちょっと背伸びして、相手に気に入ってもらおうとする。
面接官の柔らかい笑顔を見て「ここ、いい会社かも!」と安心するの、めちゃくちゃわかります。
しかし──
その笑顔、もしかしたら “人手不足でぜひ来てほしい” の笑顔かもしれません。
よくあるケース
面接官がやたら優しい → 実は辞める人が続出していて、とにかく採用したい
「うちは社員を大切にしてるから!」とニコニコ → 実際は人が足りなくて教育する余裕もない
面接官だけが良い人 → 現場はまったく別の雰囲気
入社初日、社内に一歩足を踏み入れた瞬間──
あの面接官の笑顔が消えるというのは、転職あるある中のあるあるです。
特に中小企業では、社長や幹部クラスが面接官の場合も多く、その人の人柄と実際の職場の雰囲気がまったく一致していないこともあります。

面接官の印象だけでなく、実際のオフィス見学や現場社員との面談もお願いして、現場の空気をチェックすることが大事です!
「研修制度あり」と書いてあったが、実態は「放置プレイ」
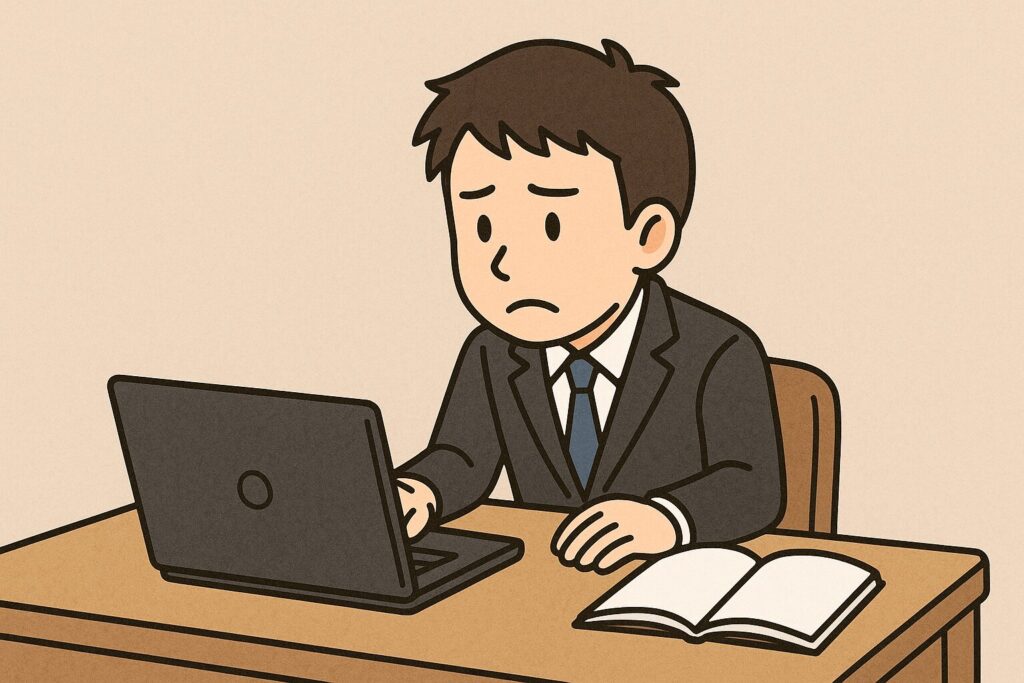
求人票で「充実の研修制度あり!」と書かれていると、
「未経験でも安心して成長できるんだ」と思いますよね。
でも現実はというと──初日からいきなり実戦投入。
誰も説明してくれないまま、「これ、お願い!」と案件を丸投げされる。
質問しても「それは自分で調べて!」で終わり。
……え、これが“研修”??
よくあるのは、
- 「先輩の仕事を見て覚えてね」→ 先輩が忙しすぎて放置
- 「最初はOJTだから!」→ OJT(On the Job Training)=自力でなんとかしろ
- 「研修資料あるから」→ ファイルはあるが誰も内容を説明してくれない
特にベンチャー企業や人手不足の会社では、「研修制度」と言いつつ、実際はそんな余裕がないケースが多いです。
結果、右も左もわからないまま、自分でググって試行錯誤。
下手すると「それ違う!」と怒られて終わる・・・新人あるあるです。

本当に研修制度が整っている会社は・・・
- カリキュラムが明確
- OJT担当者がちゃんとついてくれる
- 一定期間は成長にフォーカスしてくれる
といった仕組みがあります。求人票の「研修制度あり」は、具体的な中身を面接でしっかり聞くことが重要です!
フラットな組織です!=役職名がないだけで社長が神

求人票や面接でよく耳にする、「うちはフラットな組織なんですよ〜」
この言葉を聞いて、多くの人が想像するのは──
- 意見が自由に言える
- 年齢や立場に関係なく話し合える
- 和気あいあいとしたオープンな職場
・・・ですよね? でも実際に入社してみると、そのフラットの意味が違うことに気付くのです。
よくある実態として・・・
役職名がないだけで、意思決定はすべて社長(または創業者)が独占。
社員みんなで話し合っているように見えて、最終的には「社長が言ったから」で決まる。
つまりフラットな組織というより、 「社長が神で、その下に無名の民が暮らす国」みたいな構造となっているのです(笑)
特にスタートアップや小規模企業では、社長=創業者=意思決定者なので、このパターンが多いです。
社長のカリスマ性が強い場合、誰も意見できず、表面上はフラットでも中身はピラミッド型。
しかも厄介なのが、役職がないぶん、責任がどこにあるかが不明確になりやすい点。
プロジェクトが失敗したときに「誰の責任?」と聞くと、みんなが微妙な沈黙になる──あるあるです。

転職時に「フラットな組織」と言われたら・・・
- どういう意思決定フローなのか
- トップダウンとボトムアップのバランスはどうか
- 実際の現場で意見は通りやすいか
を聞くことが大切です。
前の会社のほうがマシだったかも…と気づくのが早すぎる

転職した直後の数週間は、本来ならワクワク期のはず。
新しい環境、新しい仲間、新しい仕事、すべてが新鮮で前職のイヤな記憶はリセットされる……はずなのに。
入社3日目でふと脳裏によぎる「……前の会社のほうが、まだマシだったかも……」
これ、転職経験者の間では 「転職ホームシック」 と呼ばれるあるある現象です。
その原因は主に3つ
特に「人間関係が原因で転職した人」が陥りがちなのが、「仕事の進め方は前のほうがスムーズだった…」という後悔です・・・。

私も心掛けましたが、ここで大事なのは「早すぎる結論を出さない」ことです。 入社直後の数週間は、誰でも環境に慣れずにネガティブになりやすい時期です。 冷静に見極めるためにも、「3か月は判断を保留する」のがおすすめです。
試用期間中に「やっぱ合わない」と悟るが、次の転職活動する気力ゼロ
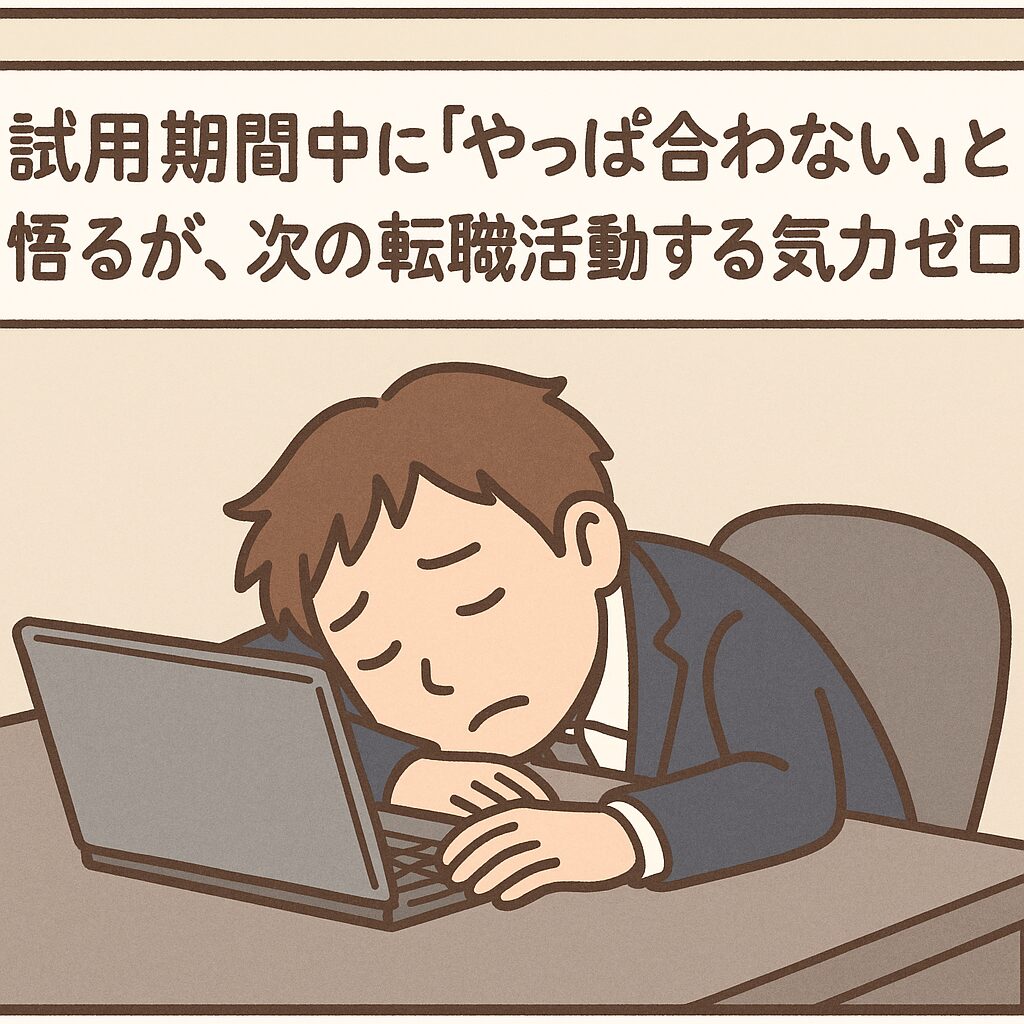
転職した直後に「ここ、なんか違うな……」と薄々感じる。
でも、「まだ試用期間だし、もう少し頑張れば慣れるかも」と自分に言い聞かせる。
──これもあるあるです。
試用期間、本来は「お互いにフィット感を確かめる期間」のはずですが、 実際には社員側だけが試される期間になっていることが多いです。
よくある心の流れ・・・
- 入社直後 → 「ちょっと違和感あるけど、まあ最初だし…」
- 1か月目 → 「いや、やっぱちょっと無理かも」
- 2か月目 → 「でもまた転職活動するの、正直しんどい…」
- 3か月目 → 気づいたら本採用されていた。
転職活動って、履歴書・職務経歴書・面接・調整…とものすごくエネルギーを使います。 一度それを乗り越えた直後に、また同じことをやる気力が湧かないのは当然です。
さらに、「短期間で辞めたら次の転職に不利になるかも」という不安も加わって、 結果としてズルズルと試用期間を乗り越えてしまい、「気づけば定着していた」というパターンも多いです。

ただし、合わないものは合わない。 無理して続けても、お互いにとって良い結果にならないケースも少なくありません。 もし明らかに「ここは違う」と感じたなら、早めに再転職の準備を始める勇気も大切です!
内定もらった時のワクワクが、初出勤5分で消える

転職活動中、内定をもらった瞬間って、最高にテンション上がりますよね。
「ついに新しいスタートだ!」 頭の中ではもう、新しいデスク、新しい仲間、ランチタイムのオシャレカフェまで想像済み(笑)
転職サイトのアカウントを削除して、「次はここでがんばるぞ!」と意気込むわけです。
──そして、初出勤当日。
受付で名乗った瞬間、出迎えた社員がボソッと一言。 「……あ、今日から来る人、いたんだ。」
その瞬間、胸に広がるのは不安と違和感のダブルパンチ。
よくあるパターンとして
そう、転職先は「自分の晴れ舞台」ではなく、会社の日常の延長。 こちらが緊張とワクワクのピークを迎えている一方で、相手は「いつも通りの月曜日」なのです。
このギャップに直面すると、わずか5分で内定時の幸福感が蒸発することもあります。
特に中小企業やベンチャーでは、入社初日の受け入れ体制が整っていないことも多く、 「自分って、本当に必要とされてるの…?」と不安になる人は少なくありません。

入社初日の歓迎ムードが会社の“組織文化”を映す鏡になることも多いので、ここは意外と重要なチェックポイントです。
「自由な社風」に期待 → ただの放任主義だった

求人票で「うちは自由な社風です!」と書かれていると、 「窮屈な上下関係がなく、のびのび働けるんだろうな〜」と想像します。
でも実際は、自由=放置というケースも意外と多いんです。
典型的な自由(放置)あるあるとして・・・
- 「何をすればいいか」誰も教えてくれない
- 「やりたいことやっていいよ」と言われても、権限も情報もない
- 相談相手がいないので、ミスしても誰も気づかない(→しかもあとで怒られる)
- マニュアルが存在しない。あるのは謎のExcelと社長と一部の社員の頭の中にだけ
つまり、自由どころか「自分で仕事を作り出さないといけない状態」です。
これは特にベンチャー企業や急成長中の会社でありがち。 「自由=自己責任」な環境が多く、主体性のある人には向いていますが、 ある程度のサポートや方針がほしいタイプの人には、ただのカオスです。
最初は「裁量があるっていいな!」と思っていても、 「何も決まっていない 」「相談相手がいない 」「頼れる上司もいない」この三重苦にハマると、「あれ?これ、めっちゃキツくない?」となりますよね。

「自由な社風」という言葉を見たら、面接時に
- どこまでの範囲が任されるのか
- 入社後のサポート体制はあるか
- 意思決定のプロセスはどうなっているか
を具体的に確認しておくことが重要です。
社内イベントが多すぎて、プライベートがない
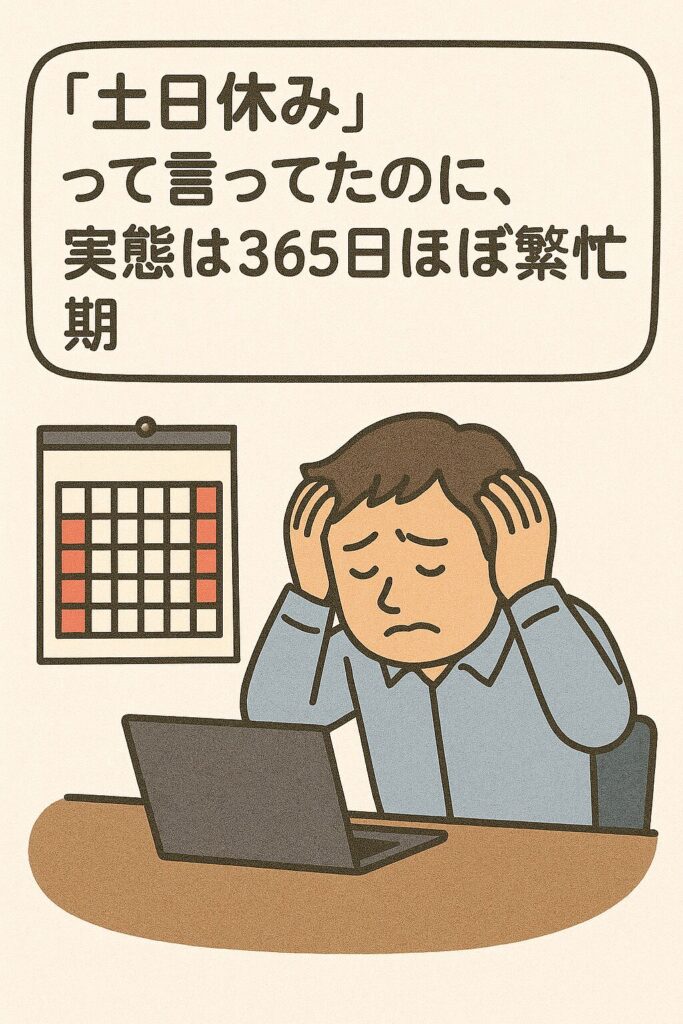
「うちは社員同士の仲がいいんですよ〜」 この一言、ちょっと楽しそうに聞こえますよね。
しかし実際に入社してみると・・・
スケジュールが会社のイベントで埋め尽くされます。
最初のうちは「みんな仲良しなんだな〜」と好意的に見えるんですが、 時間が経つにつれて「いや、これ、ちょっと多すぎじゃない…?」という感情がジワジワ湧いてきます。
特に休日や業務時間外に開催されるイベントが多いと、 「断るとノリが悪い人認定される」 「参加しないと評価に響くんじゃ…」 といったプレッシャーが生まれ、事実上の強制参加になることもあるあるです。
プライベートを大事にしたい人にとっては、これは地味にかなりのストレスです。
週末のはずなのに、いつも会社の人と一緒に過ごしている・・・
下手すると、プライベートの友人と会う時間が激減することもあります。

本当に「仲が良い」会社は、イベントに参加しなくても人間関係に影響が出ない環境です。 逆に、イベント参加が社風になっている会社は、内向的な人や家庭持ちにはつらい場合も多いので要注意です!
うちは離職率低いですよ!

面接でよく聞くこのフレーズ。
「うちは離職率が低いんですよ」これを聞くと、なんだか安心感がありますよね。
「じゃあ、働きやすい職場なのかな?」と期待してしまうのも無理はありません。
でも……その低い離職率、理由がブラックな場合もあります。
ありがちなのがこのパターンです。
つまり、「離職率が低い=ホワイト企業」とは限らないです。
特に中小企業や古い体質の会社だと、「長く勤めている=偉い」「辞めないのが美徳」という空気が根強く、 実は「社員が会社に縛り付けられている」だけのケースも多いです。
極端な例では、「有給が使えない」「定時で帰れる人がいない」「退職を申し出ると強烈な引き止めがある」など、「辞める暇も勇気も奪われる」環境すら存在します。

面接で「離職率低いんですよ!」と言われたら、 「それはなぜですか?」「平均勤続年数は?」「最近退職した人はどんな理由でしたか?」 と裏を取る質問をすると、思わぬ真実が出てくることがあります。
入社初日に「え、これ一人でやるんですか!?」案件を任される

入社初日といえば、普通はオリエンテーションや社内案内、PC設定など、ソフトな立ち上がりをイメージします。
しかし現実は──
「じゃあこの案件、今日からお願いね!」 「とりあえず、一人で進めてみて!」
……え、ちょっと待って。まだ自分、社員証ももらってないんですけど・・・
ありがちな「初日丸投げあるある」です。
こうなると、入社早々に混乱+焦り+孤独感のトリプルパンチです
「誰に聞けばいいかわからない」 「マニュアルが存在しない」 「とにかく手探りでなんとかして!」 という状況に追い込まれると、最初の1週間で心がバキッと折れる人も珍しくありません。
特に中小企業やスタートアップでは、即戦力の意味が「明日から全部任せる人」になっている場合があるので注意しましょう。
本来は中途入社に対して段階的な引き継ぎ・教育が必要なのに、それを「勢い」でカバーしようとする会社、意外と多いかもしれません。

面接の段階で、「初日はどんなスケジュールですか?」「引き継ぎ体制はありますか?」と聞いておくと、こうした地雷を回避できる可能性が上がります!
「一生ここで頑張る!」と宣言したのに、半年で転職サイトを再び開く

転職が決まったとき、内定承諾書にサインしたとき「ここで第二のキャリアを築こう!」
「もう転職はしばらくしない!」 と心に誓ったあの日。
……あれから、わずか半年。 夜な夜なスマホで転職サイトを再び開いている・・・
これは実は、転職経験者“あるある中のあるある”です。
半年以内に「やっぱ違ったかも…」と感じる理由
- 会社の文化・雰囲気が想像以上に合わなかった
- 面接で聞いていた仕事内容と実際が違った
- 成長の機会がなかった or 想像よりずっと泥臭い仕事だった
- 「ここしかない!」と思って入ったけど、冷静になると他の選択肢も見えてきた
特に「転職活動がしんどすぎて、妥協気味で決めてしまった」人は、この早期後悔に陥りやすい傾向があります。
入社前のテンションの高さと、現実の落差で心が萎えるんですね。
ただし、ここで焦ってまたすぐ転職すると、「転職癖」がついてしまう危険もあります。

まずは・・・
ことが大事です。
半年で再び転職サイトを開くこと自体は珍しくありませんが、 「次こそ同じ失敗を繰り返さない」ことが肝心ですね!
失敗も経験値になる。転職は“旅”だ!
転職に失敗はつきもの。
でも、そこで得た“リアルな現場感”は、次の転職で確実に役立ちます。
求人票の言葉をうのみにせず、実態を見極める力がつくのも、ある意味メリット!
もし今まさに「転職失敗したかも…」と感じている方、安心してください。
それ、みんな通る道です。笑ってネタにして、次に活かせばOK!です。
にほんブログ村

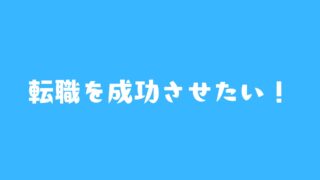
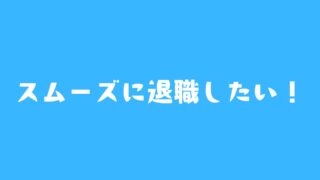

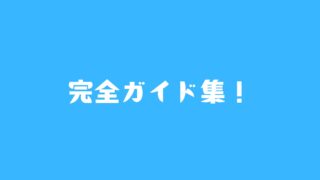




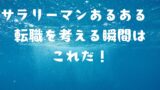

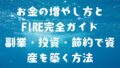
コメント