1.転職者に有利?雇用保険の給付制限期間が短縮
どう変わった雇用保険
2025年4月から「失業給付(基本手当)の給付制限期間の見直し」が施工されました。
今まで自己都合で退職した場合は、待期期間(7日間)満了の翌日から2カ月間の給付制限期間
がありました・・・結構長かったですよね。
しかし新制度では、給付制限期間が1ヶ月に短縮されました!
さらに、自己都合による退職者が、離職期間中や離職日前1年以内に、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練を自ら受けた場合には、給付制限期間は解除されます!
自己都合退職後、何らかの理由で直ぐに転職ができなかった人にとって、早期に失業給付が受給できることは切り崩す貯金も軽減される為、経済的にもありがたいですよね。
どうなる転職者
自己都合で退職せざるを得ない状況に置かれた労働者に対して、職業選択の自由を尊重し、労働者が積極的に再就職活動を行えるよう支援するために取られた措置であり、より早く失業給付が受給できるようにすることで生活の安定を図る狙いがあるのでしょう。
また職業訓練の受講により、人材不足の業界(合わせて読みたい!40代の転職 人材を積極的に募集している業界へ応募しよう)や成長産業へシフトして貰おうもとも考えているのでしょう。そうであればこの改正を機に転職を考える人も増えてくる可能性があります。
但し、5年間で3回以上の自己都合離職をした場合には、給付制限期間を3ヶ月とする規定も同時に設けられていますので転職のし過ぎは注意です!
2.転職で離職期間があるひと必見、社会保険の支払いどうすればいいの?
転職において、退職日の翌日から新しい会社の入社日となるケースが多いため社会保険(健康保険、年金)の手続きは全て次の会社で行って貰えます。
しかし、転職先の会社の事情などで退職日から入社日までに1日でも離職期間がある場合、自身で手続きが必要となります。
退職日から転職先の入社日まで空白期間がある場合、健康保険と年金の手続きが必要です。
必要な手続きが遅れると、健康保険が適用されない、未納になるなどのリスクがあるので早めに加入手続きをしましょう。
健康保険の手続きと保険料
健康保険の手続き
退職日から入社日まで空白期間が1日でもある場合は、国民健康保険への加入手続きまたは、職場の健康保険を任意継続するかどちらかを選択する必要があります。
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日からお住まいの自治体で切り替え手続きを行います。
会社員だった方が会社で加入していた健康保険は、退職日の翌日に資格喪失となります。病院などにかかると一時的に全額自己負担となり、切り替えをするまでは健康保険証がない状態になるため注意が必要です。
また、扶養家族がいる方は、扶養家族の手続きも行います。
国民健康保険への切り替えの際には、「健康保険被保険資格喪失証明書」が必要となります。転職前の会社から発行して貰えますので、マイナンバーなどの本人確認書類とともに自治体の窓口に持参してください。
但し「健康保険被保険資格喪失証明書」は会社にとって発行義務はないので入手できない場合は、事前に問い合わせて代替書類を確認して用意しましょう。
退職後、一定の条件を満たす方は、引き続き加入していた健康保険の被保険者になれます。これを「任意継続被保険者制度」と言い、加入期間は最長で2年間です。
任意継続する場合は、退職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合や協会けんぽに必要書類を提出しましょう。
健康保険料
健康保険料は、日割りではなく月割りで計算されます。月の途中で加入した場合、加入した月から保険料の支払いが必要です。資格を喪失した月については保険料が発生しません。
たとえば、5月15日に退職して5月16日に入社する場合は、転職先の会社で5月分の保険料が差し引かれます。退職日と入社日に空白期間がないため、国民健康保険に加入して保険料を納める必要はありません。
また5月15日に退職し、5月28日に入社する場合は、国民健康保険への加入がおすすめです。
なぜなら国民健康保険料は加入月から発生しますが、退職日と入社日が同月の場合は、保険料がかかりません。同じ月に入社した会社側で健康保険料が支払われるからです。
よって同月に加入と脱退があらかじめ分かっている場合は、保険料のかかる任意継続ではなく国民健康保険に加入することをおすすめします!
年金の手続きと年金保険料
年金の手続き
退職をすると、退職日の翌日に国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。そのため、退職日と入社日が空く場合、第1号被保険者に切り替える手続きが必要です。
第1号被保険者への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に自治体で手続きします。基礎年金番号がわかる書類や離職票を持参しましょう。電子申請も可能です。
国民年金の被保険者の種類は、以下を参考にしてください。
| 第1号被保険者 | 国内に住所をもつ20歳以上60歳未満の方で、第2号、第3号以外の方 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
年金保険料
退職日から転職先の入社日まで期間がある場合、国民年金保険料の支払いが発生するかどうかは、退職と入社のタイミングにより異なります。
退職日の翌日(資格喪失日)と入社日が同月の場合は、国民年金保険料が発生しませんが、空白期間が1日でもあれば、基本的に国民年金の加入手続き自体は必要です。
年金保険料は月単位で計算され、1か月分の保険料を翌月末日までに納める仕組みです。たとえば、9月分の年金保険料は10月末日までに納めます。
入社日が10月15日の場合で、異なる退職日の例で考えましょう。
退職日が9月30日:国民年金保険料の支払いは不要
退職日が9月15日:国民年金保険料の支払いが必要
9月30日に退職し、10月15日に転職先に入社する場合、9月分は元々の会社、10月分は転職先の会社が納めてくれます。
一方、9月15日に退職し、10月15日に入社する場合は、9月16日に第2号被保険者の資格が喪失します。このケースでは、新たに第2号被保険者の資格を取得するのは10月となるため、9月分の国民年金保険料が自己負担となります。
なお、国民年金保険料は、会社と折半になる厚生年金とは違い、全額自己負担となります。
保険料は2年以内に納めなければ未納となり、将来の年金が減額となります。退職後は忘れずに年金の手続きも行いましょう。
3.40代の転職 時期はいつがよいか?
一般的な良い時期とはいつ?
一般的に転職求人が増える時期は、1~3月(4月入社)、7~9月(10月入社)と言われています。
4月入社については、3月末退社の即戦力をカバーするという意味で中途採用も春に設定して採用活動を行う企業が多くなっています。
また10月入社については、賞与を貰って転職活動をする人も多いので、企業としては売り手が多い時期に即戦力や専門性の高い職種を募集する傾向もあります。
私の転職時期について
4月に転職活動を開始しして、運よく約5か月後の9月に内定を貰いました。私としては引継ぎ自体が多くない為、また早く新しい仕事にも慣れたい為、1か月後の転職も可能でしたが、先方の事情により翌年2月入社となりました。
よって9~11月まで引継ぎ、12月、1月は有給休暇を取得しました。運よく冬の賞与も貰え、また有給休暇40日も消化でき余裕のある転職ができました。
基本的には転職先の希望時期に合わせるというスタンスでしたが、このようなありがたい状況となりました。
12月に転職をした場合の注意点!
また12月に転職をした場合、12月中に給料日を迎える場合には、その会社で年末調整が行われます。その際、前職の源泉徴収票を提出する必要があります。
ただし、①前職の源泉徴収票の発行が提出期限までに間に合わない場合、➁12月に転職していても、転職後の最初の給与の支払いが翌年1月以降の場合は、自分で確定申告が必要となりますので要注意です。
12月に転職した私の知人が➁のケースでした。
12月でもその時期によって前職、もしくは現職のどちらかで年末調整が行われるのか、また確定申告が必要のか、どのケースに該当するのかを勤務先に確認することが慌てないためにも大切です。
にほんブログ村

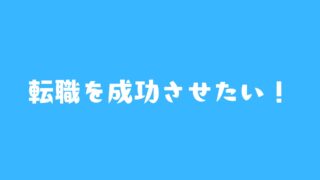
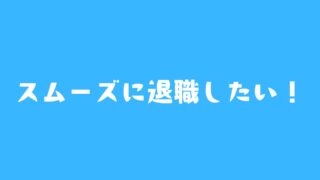

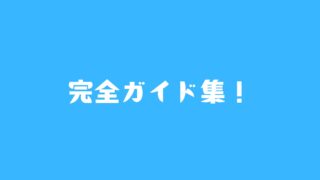
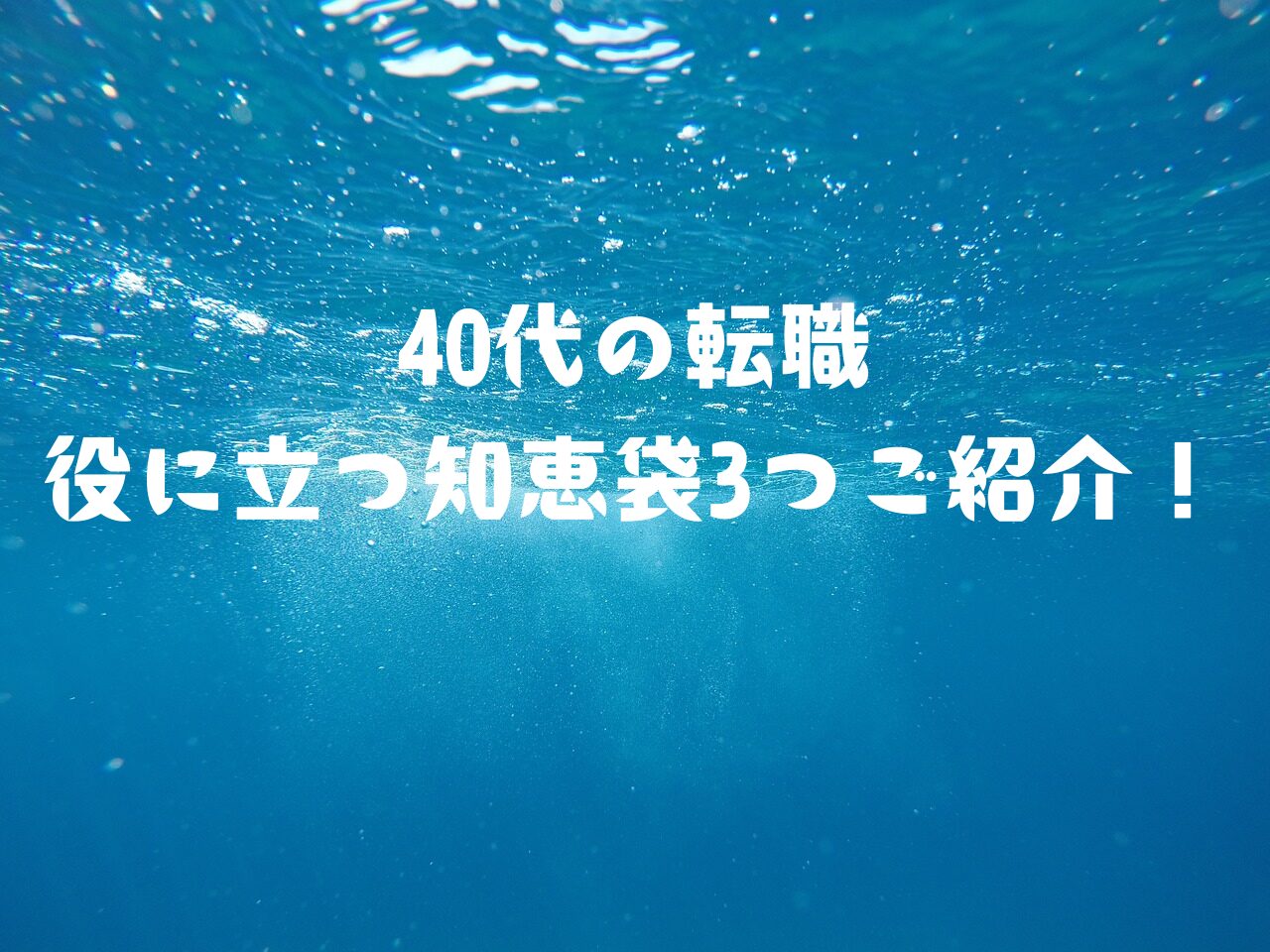

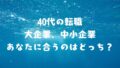
コメント